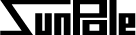column コラム
旗の文化考
世界をつなぐ「友愛の象徴」としての旗。
その可能性の先に、旗ポールの未来も見えてくる。
NPO法人 世界の国旗・国歌研究協会 共同代表 吹浦 忠正
(本コラムは、2020年12月発行の株式会社サンポール50周年誌に掲載されている吹浦忠正氏の寄稿をそのまま掲載したものです。)
目次
旗とポールの起源
有史以前、世界にはじめて登場した旗を、もし今私たちが目にすることができたら、それは衣服の切れ端を棒の先にくくりつけたような簡易なものだったでしょう。原野ではためく棒先の布切れ。ただ、その一片の布切れには意味がありました。注意の喚起であったり、何らかのメッセージであったり…。
コミュニケーションのためのツールとして生まれた旗には、そのメッセージをより多くの人に届ける必要がありました。だから次第に、より長く丈夫な棒(ポール)の先により目立つ布(旗)を付けて掲げるようになってきました。つまり旗とポールは、その起源から互いに補完しあう、不可分の関係として存在したわけです。
そして、旗は古来、集団や国家の象徴、権威の表示、所属の表示、到達すべき目標、行動のタイミングの指示、儀式などでの権威を示したり、装飾などの目的で使用されてきました。
旗の原型は世界中で見ることができますが、中国大陸はもっと早くから旗が進化を遂げた地域でした。最近の考古学や歴史学の成果によると、すでに紀元前12世紀ごろには周の開祖・武王が白い旗を用いていたとされています。恐らくこれが大陸における国旗の最古の使用例ではないか、私はそう考えています。
日本における旗、ポールの起源
では、日本ではいつから旗があったのでしょうか?
『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』(注1)には、「魏の国が卑弥呼に旗を贈った」と次のように記されています。
<その6年、詔(しょう)して倭の難升米(なしめ)に黄幢(こうどう)を賜い、郡に付して仮授せしむ。その8年、太守王頎(おうき)にいたる。倭の女王卑弥呼、狗奴国(くなこく)の男王卑弥弓呼(ひみここ)と素より和せず。倭の載斯烏越(さいしうをつ)等を遣わして郡に詣(まい)り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政(さいそうえんしちょうせい)等を遣わし、困って詔書・黄幢を齎(もたら)し、難升米に拝仮せしめ、激(げき)を為りてこれを告諭(こくゆ)す。>
その6年とは、正始6年、西暦245年にあたります。つまり文献では、3世紀半ばには日本に布製の旗が渡来していたということになります。
また、2008年(平成20)年6月27日に奈良文化財研究所が発表したところによれば、日本最古の都城である藤原宮(694年~710年)跡(奈良県橿原市)で、礫(れき)を敷き詰めた広場が出土し、南門の南側30メートルで、東西に3メートル間隔で並ぶ支柱跡が7ヵ所見つかったとあります。さらに、そのそれぞれに「幢幡(どうばん)(旗竿)」を立てた穴(直径約30センチ、深さ50センチ)が2つずつ発見された、と。旗ポールについて言えば、これが日本史上考古学的に確認しうる最古の痕跡でしょう。さらに、日本の旗ポールの由来を遡れば『日本書紀』の神武東征(じんむとうせい)神話に行き当たります。つまり、戦いの最中に金色の鵄(とび)が飛んできて神武天皇の弓の先に止まり、その金鵄(きんし)が放った光に敵が目をくらませて勝利を得たという逸話です。そこから日本の旗竿は弓を模した白黒柄、そして竿玉に金球を頂くという形になったものと思われます。ちなみに、槍が旗ポールの由来という国が多い中で、弓にその起源を求めるのは日本特有です。
注1:『三国志』魏書第30巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条の略称
漢字が示す旗文化
漢字は今から3500年ほど前に古代中国で発明されたものだと考えられています。それが4世紀後半、弥生時代の日本に伝わって現在に至っています。その漢字には「


紋章学の発展から国旗の時代へ
11世紀頃、十字軍時代の欧州では紋章学が発達しました。兜や盾に描いた紋章で所属や家柄を示し、それを取り仕切ったのが紋章官(herald)です。紋章官は、各地の騎士が一堂に会し美しく着飾って模擬戦闘をする際の仕切り役で、いわば勧進元(かんじんもと)兼呼び屋でした。彼らは、勝者を讃える詩の朗読を行い、複雑なルールを作成して紋章学(heraldry)なる煩瑣(はんさ)な規範を作り上げます。そして、こうした紋章はやがて、16世紀の絶対王政の時代になると国章や家紋に残りながらも、遠くからよく分かる鮮明な国旗へと発達していきます。
「日の丸」の誕生
では、日本の国旗「日の丸」の起源はどういうものでしょう?
平安時代初期に編纂された勅撰史書(ちょくせんししょ)(全40巻)である『続日本紀(しょくにほんぎ)』には文武天皇(在位697~707年)が701(大宝元)年元旦に、朝賀(ちょうが)の儀を行い、その場の装飾として「正門烏形幢、左日像青龍朱雀幡、右月像玄武白虎幡」が立てられた、という記述があります。訳せば、門の中央に烏、左に日像、右に月像などの標が立てられたということです。
先賢の多くは、この『続日本紀』に記された「日像(にちぞう)」が「日の丸」の起源だと言っています。新井白石(1657~1725年)しかり、国際法学者の松波仁一郎(1868~1945年)しかりです。ただ、その当時、「日像」を眺めた人々に自国の国旗だとの認識があったはずはなく、単に祝賀行事を中国の有職故事(ゆうそくこじ)にのっとった装飾儀礼で挙行することで、日本でも一通りのことができることを証明しようとしたものと見るべきだと、私は考えています。
1. 武家社会での日の丸
武家時代には、扇の図柄として多くの「日の丸」が描かれています。例えば、13世紀末(鎌倉時代)の制作とされる『前九年合戦絵詞』(国立歴史民俗博物館、東京国立博物館蔵 ※重要文化財)には、馬上の安倍貞任(あべのさだとう)(1019?~1062年)が左手に弓を、右手に「赤字金丸」の扇を持っている様子が描かれ、故事として残る源平の屋島の戦いにおける那須与一の故事はとりわけ有名です(但し、今日の日本史研究では、この話は『吾妻鏡』などに登場していないことなどから、史実ではないというのが定説です。)このように源平の時代以降、色や形はいろいろあっても、「日出したる扇」が広まっていったと言えるでしょう。また、それが日本人の太陽信仰と結んで、次第に月輪が後退し、布製の旗標となるに及び、「日の丸」の旗が確立されていったという説も成り立つでしょう。
2. 幕末の「日の丸」
幕末は、日本における国旗研究の黎明期でもありました。それは当時の切迫した国際情勢の中で始まります。その象徴的な出来事が1808(文化5)年に長崎で起こった「フェートン号事件」。38門もの大砲を積んだ英国船フェートン号が、ナポレオン支配下のオランダの国旗を掲げ、国籍を偽って渡来して貿易と薪炭(しんたん)・飲料水の提供を求め、従わなければ港内の船を焼き討ちにすると脅したのです。相対した時の長崎奉行・松平康英(1768~1808年)はフェートン号の追放を図ったものの、一門の大砲も所持していない状況ではいかんともしがたく、食料や水を提供して港を出て行ってもらうという挙に出ざるをえず、康英は国辱を一身に背負い、切腹して果てました。これを受けて幕府は、あらかじめ決めた約束に従って各種の旗を順番に挙げて偽装を防ぐ「旗合わせ」をオランダ船との間で行うようになりました。
こうした窮地で、日本における国旗の研究は始まりました。しかし、当時の国旗研究はオランダを通じて入手する図表などによるほかはなかったでしょう。ただ学問的な資料のない中で、研究者たちは各地で情報を交換し合い、懸命に「有事」に備えたものと思われます。ペリーが31星の「星条旗」(注2)を掲げて浦賀にやって来たのは、そんな最中の1853(嘉永6)年のことでした。
緊迫した国際情勢の中、徳川幕府も「日本の惣船印」を決定する必要に迫られ、「日の丸」を公式に採用しました。1854(嘉永7)年7月11日、老中首座の阿部正弘は「大船製造につきては異国船と紛れざるやふ、惣船印は、白地日の丸の幟相用い候やふ仰せでられ候」と通達しました。ところが、外国との接点が急に増えた幕末になって、「日の丸」を直ちに国旗とすることについては異論もあり、幕閣は一度、「白黒白の横三分割旗」とでもいうべき、新田家(徳川の先祖とされる)の紋章に由来するデザインの旗を、「日本の惣船印」に決定したのでした。当時、「日の丸」は幟に1~5個描かれて、御用米(幕府の米)の輸送にあたる船の旗だったからです。
そこに毅然として今日の「日の丸」の原型を提案したのが島津斉彬です。紆余曲折あったものの、斉彬は親交のあった水戸の徳川斉昭の協力を得るなど手を尽くして異論を封じ込めました。このあと、斉彬は1855(安政2)年に洋式帆船「昇平丸」を幕府に献上。「日の丸」を船尾に掲げて品川沖に停泊しました。これが「日の丸」が日本の国旗として船舶に掲揚された第一号となったのです。
注2:アメリカ合衆国の国旗「星条旗」の星は州を示しており、50州ある現在は50の星が配されている。ペリーが日本に来航した当時は31。ちなみにアメリカ独立時には13の星が輝いていた。
3.明治維新でも変わらなかった「日の丸」
明治維新は、政治史的にはある種の革命でした。革命の主眼がそれまでの政治経済体制を根幹的に変更することだとすれば、幕府の御用米運搬船に使用され、対外的には阿部正弘以下の幕閣が決定し、「惣船印」とした「日の丸」が採択されたのです。「菊の御紋を」という声もあったとも聞きますが、現実にはそうなりませんでした。それだけ、「国旗は日の丸」という意識が浸透していたということでしょう。
明治維新の最後の戦いである「箱館戦争」では、榎本武揚麾下(きか)の旧幕軍は「日の丸」を用い、攻め込む新政府軍は「旭日旗」でした。しかし、各国に、正式に政権を移譲された正当な政府であることを示す必要があった明治政府は、「箱館戦争」から数ヵ月後の1870(明治3)年1月27日(旧暦)に、太政官布告白第57号で「日の丸」整備の第一歩を記しました。
「日の丸」と旗ポールの意匠
今、国旗には定められたデザインがあります。
例えば、日本の「日の丸」では縦横比は2対3、円の中心は対角線の交点と一致し、縦の長さの5分の3を直径とした円を描いて白地に紅色の日章とする(国旗国歌法)とされています。
一方、旗ポールにはデザインの規定は存在しません。せいぜい、同じ太政官布告で「何時から何時まで掲揚しろ」とか「雨が降ったらどうしろ」とか、旗の使い方を定めている程度で、それもポールのデザインについての定めではありません。ただ、伝統的には日本の旗竿の特徴は白と黒の縞模様とされています。この由来が『日本書紀』の神武東征にあることは前述しました。また、日本では金球が使われる竿玉についても言及すると、これこそ各国各様で、アメリカではポールの先に付くのはホワイトイーグル、韓国では国花でもある無窮花(무궁화;ムグンファ;むくげ)の花、スリランカでは蓮の花といった具合。ポールと国旗とを合わせて眺めると、いっそう興味深い文化史が見えてきます。
旗の未来は?
先日、テレビで水泳の競技中継を見ていて、驚いたことがありました。選手が水に飛び込んで泳ぎ始めると、一人ひとりが泳ぐ姿に重ねて、その選手の属する国の国旗や順位、泳ぐスピードなどがCGで表示されるのです。確かに分かりやすい。感嘆と同時に、IT技術の進歩は布とポールからなるリアルな国旗を淘汰してしまうかもしれない、とそんな思いが頭をよぎりました。
しかしそれは、私の取り越し苦労に終わるでしょう。国旗、旗とはかけがえのない文化ですから。目印としての旗はあるいはCGなどに変わるかもしれません。しかし、権威の象徴としての旗には「現物であること」が求められます。オリンピックで、次期開催都市の市長にオリンピック旗を手渡すという行為は、まさに現物がなければ成り立たない荘厳な儀式です。文化の象徴としての旗の役割は永遠になくなることはない、と私は思っています。
喜びを共有するための旗
また、最近スポーツの競技中継を見ていて、大変喜ばしく思うシーンがあります。それは例えばワールドカップで、左右の頬に自国と対戦相手の国旗をペインティングして応援している姿。試合を終えて、両国のサポーター同士が抱き合って健闘をたたえ合う姿…。先日、フィギュアスケートの競技大会に行ったときには観客席のほとんど全員が国旗を振りながら応援をしている様子を好ましく見ていました。
旗には、そもそも喜びが伴います。インターナショナルスポーツの発展で、旗を振りながら互いに喜び合う、旗を介した友愛の文化が目に見える形で育まれているように感じます。国旗に込められた愛国心も、その本質に互いを尊重・尊敬し合う“enlightened”な思いがなければならない。国籍や民族などの違いに阻まれることなく、友を愛し、恋人を愛し、家族を愛し、故郷を愛する。その延長が、国旗であってほしいと思います。そういう意味では、ますます旗を普及させていかなければならない、と思います。人々が喜びを共有し、思いを分かち合うための旗を。そこにサンポールが果たすべき役割と責任は決して小さくはないでしょう。
本コラムは、2020年12月発行の株式会社サンポール50周年誌に掲載されている吹浦忠正氏の寄稿をそのまま掲載したものです。
著者プロフィール
吹浦 忠正 ふきうら・ただまさ
1941(昭和16)年、秋田市生まれ。早稲田大学大学院政治学科修了。
現在、NPO法人世界の国旗・国歌研究協会共同代表、NPO法人ユーラシア21研究所理事長、朝日新聞社フォトアーカイブ担当アドバイザー、法務省難民審査参与員。オリンピック東京大会(1964年)組織委員会国旗担当専門職員、長野冬季オリンピック大会(1998年)組織委員会儀典担当顧問、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会国際局アドバイザー、埼玉県立大学教授を歴任。内閣府オリンピック・ホストタウン国旗講座講師就任。
「国旗と儀典の専門家」として知られ、「週刊新潮」で「オリンピック・トリビア」を4年半連載。国旗関連の著作は46点以上にのぼる。2018年度からの「道徳」の教科書に主人公として登場。TVにも多数出演し、NHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」、「青天を衝け」(渋沢栄一)」の国旗考証も担当。近著は『オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌(CD付)』(三修社)。「小学道徳 生きる力」6年連載、自民党広報誌「りべら」、「公明新聞」、「毎日小学生新聞」連載。