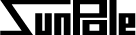column コラム
ポールの道具考
道具の発祥は「棒と器」。
「棒(ポール)」は人類の創造性の原点。
その考察から、次の創造が、始まる。
株式会社GKデザイン機構 相談役 山田晃三
(本コラムは、2020年12月発行の株式会社サンポール50周年誌に掲載されている山田晃三氏の寄稿をそのまま掲載したものです。)
序:サンポールの「ポール」
「サンポール」という社名は、輝く太陽のもとではためく旗と、それを支えるポールの姿を描いたネーミングだと聞いている。順風を受けとめ、旗もポールも共に光輝く姿は、企業の未来を連想させる良き社名だ。しかし現実はそうとは限らない。風の無い日があれば曇った日もある。嵐や吹雪に耐える日もあるだろう。それに一日の半分は夜だ。月明かりのもとで誰にも知られずはためいていることもある。旗もポールも良く知っている、輝ける日はそんなに多くはないことを。耐えなければならない毎日がいかに多いことか。とくに「ポール」は主役である旗を支え、掲げるというその役目を全うしようと日々寡黙に直立しているのである。旗が無くともそこに立ち続けている。
そんな「ポール」とはいかなる道具なのだろう。様々な角度から思索してみたいと思う。そもそもこの「ポール」、その出生はいかなるものなのだろう。
その1:道具の発見と人類の誕生
いまから数十万年前、ヒトはサルから人類への道を歩みはじめた。この人類誕生の瞬間をみごとに描き出したSF映画がある。1965年に公開された、アーサー・C・クラークとスタンリー・キューブリックによる歴史的名作「2001年宇宙の旅 2001:a space odyssey」である。この映画の冒頭、サルが人類になるという象徴的シーン「人類のあけぼの」を紹介したい。
延々と広がる岩場に、小さな水場を奪い合うふたつのサルの集団がいた。いっぽうのボスザルが、近くに落ちていた獣の「白い大腿骨」を握りしめ、敵のボスザルの頭をたたき割った。水場を奪い返した彼は、勝利の雄たけびとともに握りしめていたその骨を天高くに放り投げる。白い骨はスローモーションでゆっくりと回転しながら(ヨハン・シュトラウスの「美しき青きドナウ」が流れ)、西暦2001年の宇宙船にその姿を変える。初めて道具を手にした人類誕生の瞬間をみごとに表現している。「大腿骨」という道具が、素手の数倍の力を彼に与えた瞬間であった。
道具のはじまりは、ヒトの身体機能の拡張にあると想定できる。この握りやすい「大腿骨」は、彼の手が、拳が、より強くなって生まれかわったものだ。より強く生きたいと希求し、やがて矢じりや槍をつくりだす。さらに人類は武器ばかりでなく身体機能の延長線上に強力な人工世界をつくりあげ、生活全般を道具によってサポートさせた。先の宇宙ステーションは、地球からも離れて生きる人類の、究極の道具の姿である。
その2:「棒と器」の二大発明
道具のはじまりは獣の骨の活用であった。のちに道具を加工するようになり木や石を用いて「斧」や「槍」をつくりだす。獲物を獲得するために無くてはならない狩猟道具たちが生まれた。しかしここで、大きな見落としがある。斧や槍といった攻撃的な道具のいっぽうで、器(うつわ)という道具たちも平行してつくられていた。
獣の屍には、棒状の骨ばかりでなく「頭蓋骨」という骨がある。割れてひっくり返り、雨水がこの頭蓋骨に溜まっているのを見つける。手のひらではなく頭蓋骨を道具として水を運んだり飲んだりすることを発見している。植物のヒョウタンも器として使えることに気づき、様々な大きさの器が考案されたと想像できる。
ここに、大腿骨から進化した斧や槍に代表される「棒」系の道具たちと、頭蓋骨やヒョウタン、貝殻などに代表される「器」系の道具たちという二系統の道具が、道具進化の源にあったことを知るのである。この道具の原始二分類を「棒族と器族」と呼ぶ。棒族は能動的作用を基本とし、破壊や突破、搾取、撹拌を得意とする。器族は受容的作用に長け、保存や保護、醸造、育成を得意とする。
道具の進化は、この両者の協力関係、融合、一体化にあるといって過言ではない。たとえば、槍は、矢のように遠くへ飛ばしたほうが安全で効果的だ。そこで弓が発明される。弓はエネルギーを貯める受容の道具、器族だ。矢と弓、両者の協力が狩猟道具を進化させた。すり粉木とすり鉢、鍵と錠、ペンとノート。帚(ほうき)と塵取(ちりとり)はのちに一体化し、電気掃除機に進化した。
その3:「旗竿」への進化
ここで「旗竿」という道具について考えてみたい。
旗を掲げるための「竿」であるから、これは間違いなく棒族である。棒族には能動的作用があるという前提からすれば、竿は旗を掲げながら移動し、見せつけ、振り回し、戦場においては突撃の頭(かしら)ではないかと思う。旗竿はそこにじっと立っているというよりは、人の手にあり、必要に応じて移動させる道具と推測される。その先端に「旗」という性質の違う道具を取り付けたのである。では旗とはどのような道具か。
旗は布など軽く風になびく素材に色彩や記号、文字などを配した情報の集合体である。白いキャンバスに情報を書き留めるという機能からすれば旗は器族である。ここにも棒と器の二大分類が成立している。「竿と旗」このふたつは全く性質が異なるがゆえに良きパートナーである。
旗竿を調べてみると、戦場においては「槍」がその原型にあるように思う。槍の先に留められた旗は、自身が何者かを示し、その力の強さをアピールするための標(しるし)。そこでこんなことを想像してみた。
狩猟採集の原始の時代、木の先を尖らせた「槍」を手にし集団で獲物を探す。小動物ネズミを一刺しして捕まえた彼は、きっとそのネズミを高く掲げ、仲間たちにいま捕らえたことを知らせたに違いない。遠くから暴れるネズミのシルエットが良く見える。旗竿は、こんな気持ちを伝える道具として進化したものではないかと思う。
その4:「竿」の生態系
旗竿は、本来そこにじっとしているものではない、と記した。ならば設置された国旗掲揚のポールは、どこに棒族的能動性があるのか。これには解がある。風である。風が吹くことで初めて旗は情報伝達の役割を果たす。これは相対論である。風を切るようにポールが走っているのである。船舶の、マストの頂上の旗も、マストという竿の移動で、はためいていられる。また、その船舶の「帆」は空気をはらむ器族。そうしてみれば帆もマストに対する旗のような存在ではないか。
「竿」とは棒族の原点と言っていい道具である。字体の原義は竹の葉を取り去ったもの。私は釣りが好きで、いつも竹竿(bamboo rod)を愛用している。ロッドの先に糸(line)を付けて、疑似餌(fly)を飛ばす。疑似餌は魚への餌という(旗ではないが)情報である。
「物干竿」も横にしか使わないが、いろんな色やかたちの洗濯物を掲げる。人に見せるつもりはないが、洗濯物は見る人にとっては興味深い。旗とはいわないが見ようによっては旗と同じではないか。
「竿師」という言葉がある。竿をつくる職人ではなく、隠語で男性機能を使って仕事をする人である。サオという棒族の性質を端的に表している。棒族的性質から道具を分類すると、たとえばカメラなどもレンズを通して獲物を撃つ(shot)という意味では棒族、それを納めるフィルム(memory)は器族である。両者仲良くいまに生きている。
竿、そしてポール。棒族は世の中の至るところに存在しているが、その生き方は多様で一概に能動的ともいえず、しかし器と共にあり、さらに変化に富んでいる。
その5:旗竿のこころ
道具とは、人間の身体機能の延長線上につくりあげた人工物を指すことばである。獲物を捕らえたいと思う意志が、手の延長線上に槍や弓、拳銃をつくりあげた。速く走りたいと思う意志が、足の延長線上に車輪を見つけ、自転車や自動車をつくりあげた。より強く、楽しく過ごしたいという強烈な人類の欲求が多様な道具を誕生させ、この地球上に強大な人工世界をつくりあげた。自らの欲望を成就するために道具を生みだしたとするのならば、その道具たちをしっかり観察すれば、当事者の「欲」が見えてくる。作る人と使う人のこころが乗り移っているかのごとくである。道具はヒトの分身、化身といっても間違いではない。よって道具にも「こころ」がある。
「旗竿のこころ」というものを想像してみたことがあるだろうか。サンポール製の旗竿が、小学校の校庭に並んで立っている。晴れた日の運動会では、日章旗が掲揚され多くの人たちの注目の的だ。先にも述べたがこれは数少ないハレの日。ポール自身もこのときは見つめられて高揚している。しかしふだんは雨風に耐え、風景の一部としてじっと立ちっぱなしだ。雨や嵐、泥や埃を被ることもあるだろう。暑い日も寒い日もがんばっている。そして10年、20年と自身も年老いていく。旗竿にも生があれば死がある。
私たちは、自然には神が宿り、道具にはこころがあると教えられてきた。山川草木虫魚、道具や建築に至るまで、あらゆるものに生命(いのち)が宿っている。しかもみな平等な生命だ。私はいつもそんな眼差しで「旗竿」を見上げていたいと思う。
結:ポールの未来
ポールに絡まりつく旗を見て「何とかならないものか」とサンポールの創業者は思った。写真師であったと聞くからその観察力はカメラを通しての鋭さがあったと思う。きっと旗や竿の苦しげで、たまらない気持ちが読めたのだと思う。不自然さを感じた彼の美意識が、問題意識を誘発させた。
「旗ポール」をつくり研究するうちに、ポール製作の技術をマスターしていった。そんな中から「クルマ止め」が誕生した。クルマ止めは攻撃ではなく「防御」の道具。矛(ほこ)というよりも盾(たて)である。形は棒状であるが、役割は盾。しかしこれは矛盾してはいない。刀もときに身を守る。敵の攻撃を刀をもって防御する。突っ込んでくるクルマが敵の刀ならばクルマ止めはそれを受けとめる。
さらなる「ポール(棒)の研究」が次なる創造の出発点になるのではないだろうか。あるいは旗が本来持っていた情報伝達機能が、次なるポール開発のヒントになるかもしれない。クルマ止めなる道具は、物理的な防御の道具ではなく、おそらく精神的な注意喚起や、エリアを示す表示機能にも優れている。
領域間の境界を示すのもポールの役割だろう。ポールは意匠によって、ときに地域の象徴となるほどに存在感が高い。津波に流されず生き残った一本松は、歴史を背負ったシンボルとして、心象に深く刻まれている。
サンポールには、誇り貴き「道具の原器」がある。さらに道具のこころが読める。人のこころに寄り添う道具たち、みなに愛される道具たちを、これからも生みだし続けて欲しいと私は願っている。
(本コラムは、2020年12月発行の株式会社サンポール50周年誌に掲載されている山田晃三氏の寄稿をそのまま掲載したものです。)